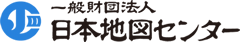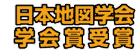東京時層地図―ピンポイント紹介
ピンポイント紹介
東京・丸ノ内

文明開化期:明治 9-17年 測図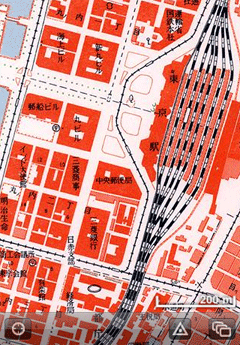
高度成長前夜:昭和30-35年 修正
現在、金融・経済の中心地の一つである丸ノ内は、明治初期は陸軍練兵場、警視庁、監獄署などが立地する官有地でした。これらの施設は移転し、跡地を岩崎弥太郎(三菱財閥の創業者)が買い取り、現在のような三菱グループが多く立地する丸ノ内が形成されました。
上記の南側に立地する東京都庁舎は、明治27年に東京府庁舎として完成しました。平成3年には、東京都庁舎は新宿に移転し、その跡地には東京国際フォーラムが建設されました。
品川
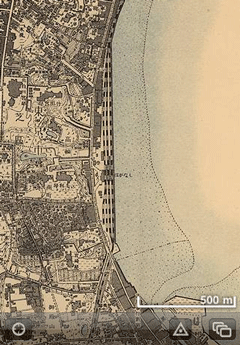
明治のおわり:明治39-42年 測図
現代:航空写真(Googleマップ)
品川駅はJR東日本(東海道線などの4系統)、JR東海(東海道新幹線)、京浜急行電鉄が乗り入れる巨大ターミナル駅です。
草創期の品川駅は、左図を見てわかるように路線の東側一体が海でした(現在の港南地区)。鉄道唱歌にも「窓より近く品川の 台場も見えて波白き 海のあなたにうすがすむ 山は上総か房州か」と歌われています。
時が経過するにつれ埋め立みが進み、現在では、オフィスビルや商業施設が立地するビジネス街になりました。
羽田
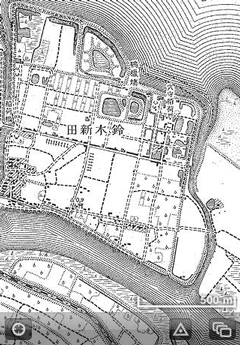
明治のおわり:明治39-42年 測図
現代:航空写真(Googleマップ)
10月21日に国際線が就航する羽田(東京国際)空港。開港以来、日本を代表する空港の一つとして発展を続けています。そのような羽田空港も明治の頃は、海苔や貝を養殖していた漁師町でした。そこには、五穀豊穣・商売繁盛の神として日本全国から参拝者が訪れる穴守稲荷神社がありました(左図)。
現在の京急空港線は、もともとはこの神社への参拝鉄道として誕生しました。また、神社の北西近くには鉱泉があり、温泉宿や料理屋などが建ち並ぶ観光地として、当時は大いに賑わいを見せたといいます。
大正時代に入ってから、この周辺は空港としての整備が進みました。終戦直後には、空港拡張に伴う強制退去が実施され、近隣住民は余儀なく移転させられました。しかし、神社の大鳥居だけは撤去されず、空港駐車場内に残された状況でしたが、平成11年に新滑走路整備によって海老取川の河口に移設しました。